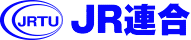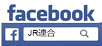HOME > 交通政策
JR連合は、「鉄道の特性を活かした持続可能な交通づくり」を標榜し、「21世紀鉄道ビジョン」「JR20年の提言〜7つのパートナーシップ〜」「次なる30年の強くしなやかなJR産業を創る5提言」等の政策提言を発信するなど、その具現化に向けて政策活動に取り組んできました。とりわけ、交通政策においては、人口減少や少子高齢化に加え、コロナ禍等による社会の変化により、公共交通を取り巻く環境が一層厳しさを増しています。私たちJR連合は、あるべき公共交通の姿からバックキャストの考え方により、必要な交通政策を発信し、その実現に向けて取り組んでいきます。
JR連合交通政策の沿革
JR連合重点政策集2025-2026 (2025年4月)
JR連合は、この間、産業政策を運動の重要な柱と位置付け、日本経済・社会の発展と地域の活性化に資する総合交通体系の構築、産業の明るい展望の創出に向けて活動を展開してきました。そして、働く者の視点から各種政策課題を抽出するとともに、課題への短期的な対処方はもとより、今後の鉄道をはじめとする公共交通の中長期的なあるべき姿・方向性についても議論し、継続的な取り組みを進めてきました。
これまで、産業政策のうち、特に交通政策に関する課題を取り扱ってきたことから、「交通重点政策」として策定を図ってきました。今般、JR産業の裾野の広さ、そしてそこで働く組合員が直面している課題にも目を向け、産業一体となって政策課題の解決に取り組むことを視野に入れ、JR産業全般に関わる課題も取り上げる「JR連合重点政策集」を策定しました。
引き続き産業の政策課題の解決、政策要望の実現に向け総力をあげて取り組んで参ります。皆さまの一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
地域活性・発展の礎となる鉄道網の構築を目指して (2023年2月)
〜高速鉄道・新幹線ネットワークの構築と計画推進に係る政策提言〜
「もはや日本に高速鉄道・新幹線をつくる必要はないのか?」
私たちの認識は違います。人が移動し集い、交流することで新たな価値が創造されるほか、長距離通勤や二拠点居住といった新たなライフスタイルの促進など、高速鉄道・新幹線を活用した持続可能な社会の形成が進みつつあります。広域・高速の移動を担う新幹線の営業と建設に携わる仲間で構成するJR連合と鉄道運輸機構労働組合は、わが国の社会・経済の発展には高速鉄道・新幹線ネットワークの構築が必要不可欠であると考えており、その実現に向けて現状と課題を整理し、実現させるべき政策を提言します。
持続可能な地域公共交通をつくるJR連合政策提言 (2022年2月)
人口減少・少子高齢化が進み、地方路線は大量輸送に適した鉄道の特性を発揮できずご利用が大きく減少しています。この課題認識は、2017年に策定した「JR連合鉄道特性活性化プロジェクト最終提言」にも盛り込まれていますが、そこにコロナ禍が拍車を掛けています。採算事業の利益を不採算路線に充当する「内部補助」はもはや限界にあり、持続可能な政策への転換が求められています。JR連合は、離職増加に歯止めをかけ、次代を担う人財を確保し、JR産業を将来に向けて魅力的で持続可能な産業にするべく、地域公共交通が抱える課題をとりまとめ、働く者の立場から提言します。
◇ 各種プロジェクト
JR二島・貨物経営自立実現プロジェクト (2019年11月〜2022年6月)
JR連合は、JR北海道、JR四国、JR貨物の経営自立を実現すべく、「鉄道ネットワークのあり方」と「経営のあり方」を一定切り分けた上で将来像を明確にし、2021年度以降の新たな支援実施等を通じて、その道筋を示していくことなど、具体的な提起とすべく取り組みを進めています。
中長期政策課題プロジェクト (2012年9月〜2017年6月)
JR連合は将来の鉄道・将来のJRを見据え、中長期的視点に立脚した政策課題に取り組みました。
JR25年にむけた政策提言 (2011年6月)
〜国鉄改革を完遂し持続可能な交通体系を築くために〜
JR各社は2012年4月で発足25年を迎えます。JR連合は、JR25年の節目にむけ、あらためて鉄道をはじめとした公共交通の飛躍にむけて提言します。
総合交通体系に基づく交通政策の基本的方向 (2010年3月)
−持続可能な交通体系形成のための提言−[交通基本政策検討委員会答申]
JR連合は、2009年9月に「交通基本政策検討委員会」を設置し政策提言の策定に取り組んできました。「交通政策の基本的方針」の確立を通じて私たちの政策提言を実現するために、総合交通政策の確立に向けた同委員会の答申である「総合交通体系に基づく交通政策の基本的方向−持続可能な交通体系形成のための提言−」を提起します。
交通基本政策検討委員会緊急提言 (2009年11月)
〜高速道路をはじめとする自動車利用者の負担軽減に対する考え方〜
民主党政権が進める高速道路無料化施策に対し、総合交通政策の視点から、JR連合としての緊急提言をまとめました。
モーダルシフト推進のための提言 (2009年6月)
JR連合は、鉄道貨物の発展、活用にむけた中期的な政策実現をはかるための政策提言を策定しました。
JR20年の提言 - 7つのパートナーシップ - (2007年6月)
JR発足20年を迎え、「21世紀鉄道ビジョン」をベースとしながらも、鉄道の持続的発展と今後の10年を展望して、「7つのパートナーシップ」として整理した「現状と課題」を踏まえ、「今後のあり方」を明らかにし、その実現にむけて必要となる「国・地方自治体の役割」と「JRの役割」について提言をまとめました。
21世紀鉄道ビジョン (2003年6月)
JR連合は、「鉄道の特性を活かした、自動車に過度に依存しない、接続可能な交通づくり」を指向していくべきだと考えています。今後10年程度を展望し、国民、利用者に選択され続ける鉄道づくりを目指して、「21世紀鉄道ビジョン」を策定しました。